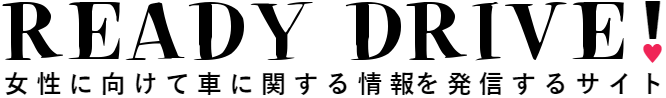EVのメリットとデメリット
電気自動車(EV)は走行中に排出ガスをほぼ出さず環境負荷を大きく軽減できます。
モーター駆動のため発進時の加速がスムーズで静粛性が高く、街中での乗り心地が快適です。
さらに、電気代はガソリン代に比べ安価なので、一定距離を走った場合の燃料コストはガソリン車より低く抑えられることが多く、オイル交換やエンジン周りの整備が不要な点を含めるとランニングコスト全体でメリットが出やすいです。
一方、デメリットとしては車両本体価格が高めであることが挙げられます。国や自治体からの補助金や税制優遇を受けられる場合もありますが、初期投資はガソリン車に比べ高額になりやすいため、総合的な費用対効果を検討しましょう。
また、急速充電を利用しても80%まで充電するのに約60分かかる場合が多く(車種や充電器の出力により前後します)、旅先で充電スポットが混雑していると待ち時間が発生するリスクがあります。
さらに、バッテリーは低温下で性能が落ちやすく、冬季にはカタログスペックより20~30%程度航続距離が短くなるケースがある点も覚えておく必要があります。
注目の新型EVモデル紹介
最近国内外のメーカーから多彩な新型EVが登場しています。
まず日産「アリア」は、上位グレードの「B9 e-4ORCE」でWLTCモード航続距離約610kmを実現しており、急速充電(90kW対応時)なら80%充電まで約60分で完了します。静かで上質な内装も魅力です。
トヨタ「bZ4X」はSUVフォルムながら全輪駆動モデルも選択可能で、航続距離は前輪駆動モデルで約516km、四輪駆動モデルで約470km(WLTPモード)とされています。補助金を活用すると購入しやすい価格帯になる点もメリットです。
スバルとトヨタの共同開発による「ソルテラ」も見逃せません。AWD車はWLTCモードで約542km、FWD車なら約567kmの航続距離を誇り、雪道や山道など過酷な路面でも安定した走行が期待できます。
海外ブランドではテスラ「モデル3 パフォーマンス」が依然として人気です。WLTCモードで約605kmの航続距離を実現し、0–100km/h加速は約3.1秒と圧倒的な速さを誇ります。テスラ独自のスーパーチャージャー網を利用できる点も大きな強みです。
コンパクトセグメントではホンダ「e:Ny1」が近々国内発売予定で、WLTPモードで約412km走行可能とされており、都市部の取り回しや通勤からレジャーまで幅広く活躍できる性能を備えています。
購入時のチェックポイント
EVを選ぶ際には、まず「実際に必要な航続距離」を見極めましょう。
通勤距離や週末レジャーでの移動距離を想定し、カタログスペックだけでなく季節変動(冬季には20~30%程度航続距離が落ちる)を考慮したうえでバッテリー容量を選ぶことが重要です。
次に「充電インフラの整備状況」を確認しましょう。自宅に普通充電設備(100Vまたは200Vのコンセントや専用充電器)があるか、近隣に急速充電器が設置されているかを事前に調べることで、日常の利便性が大きく変わります。地方では充電スポットが少ないエリアもあるため、充電アプリやカーナビで充電スポットの空き状況を把握しておくと安心です。
充電規格も要注意です。日本ではCHAdeMOが多く普及していますが、テスラや海外勢ではCCS方式を採用しているため、急速充電器利用時に互換性があるかどうかをしっかり確認しましょう。
また、国や自治体の補助金・税制優遇を活用すると初期費用を数十万円単位で抑えられる可能性があります。補助金額や申請時期は自治体によって異なるため、最新情報は各自治体のウェブサイトで確認し、期限内に手続きを行うことが大切です。
さらに、車両価格だけでなく「トータルコスト」を意識しましょう。バッテリー交換費用や保険料、定期点検・タイヤ交換といったメンテナンス費用を含めた生涯コストを見積もり、比較検討することがポイントです。
最後に「保証内容やアフターサービス」も忘れずにチェックしましょう。バッテリー劣化保証の期間や走行距離保証範囲、故障時のサポート体制(代車提供やリースバックなど)が充実しているかを購入前に販売店で確認し、万が一のトラブルに備えておくと安心です。